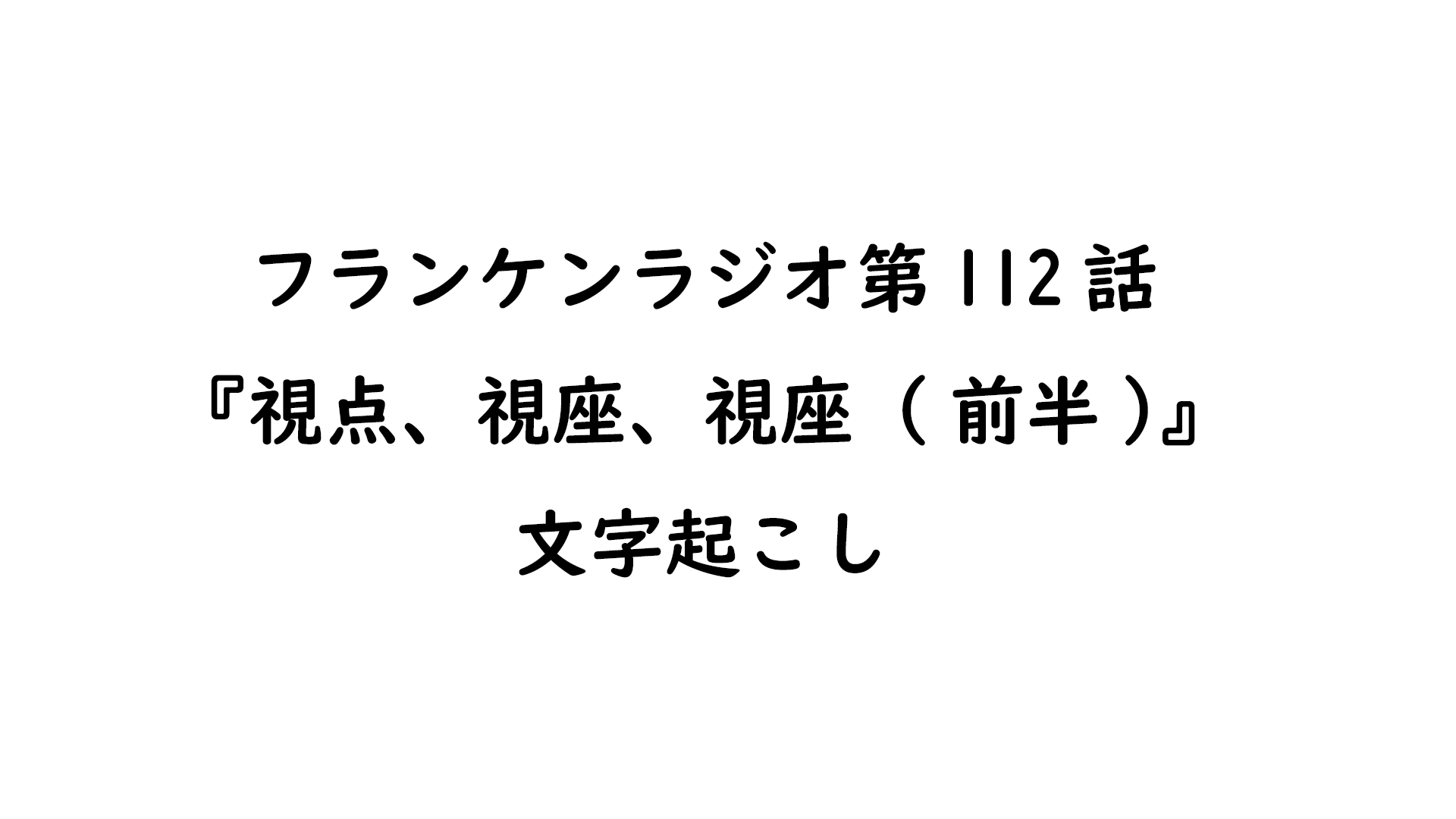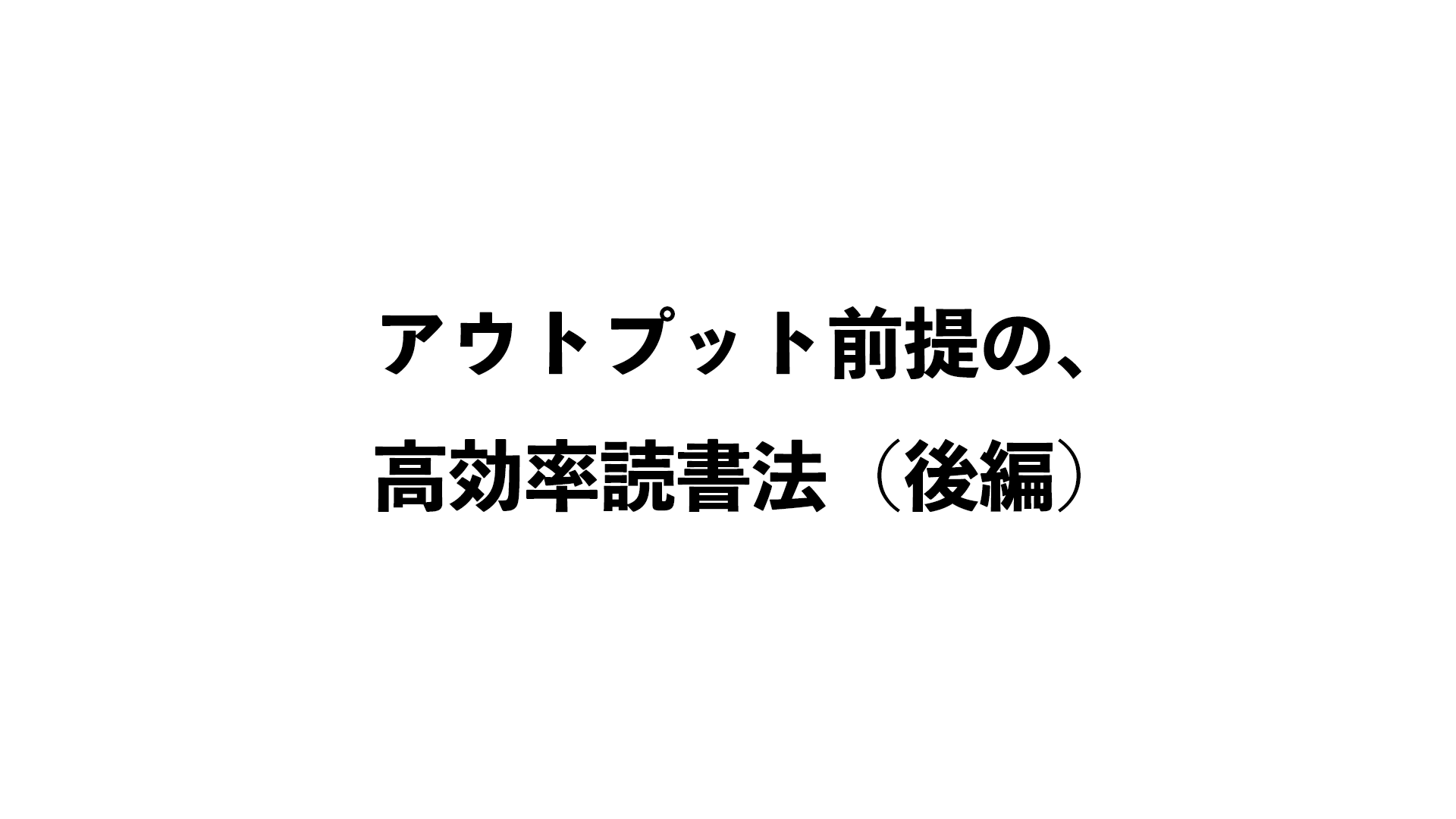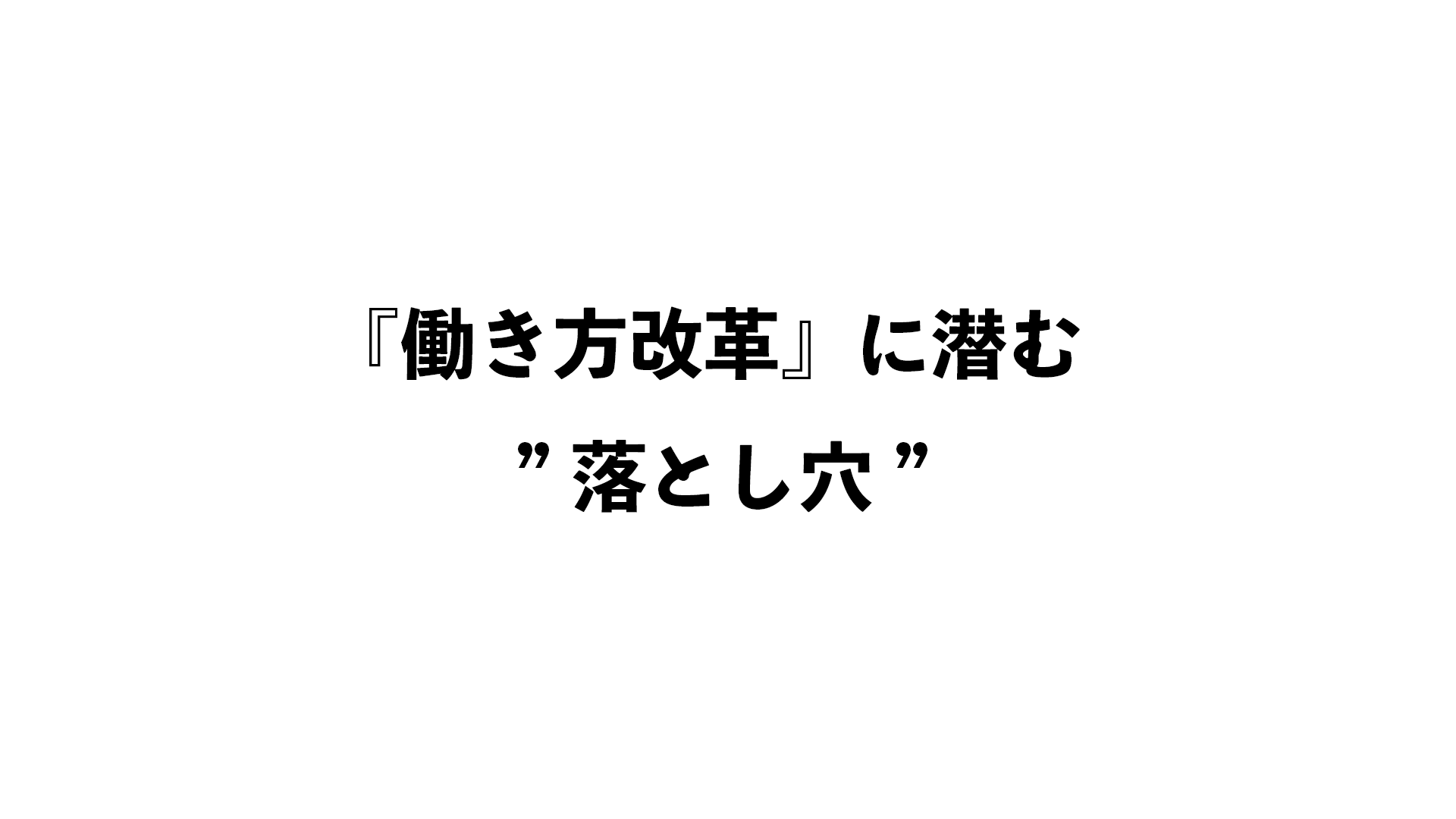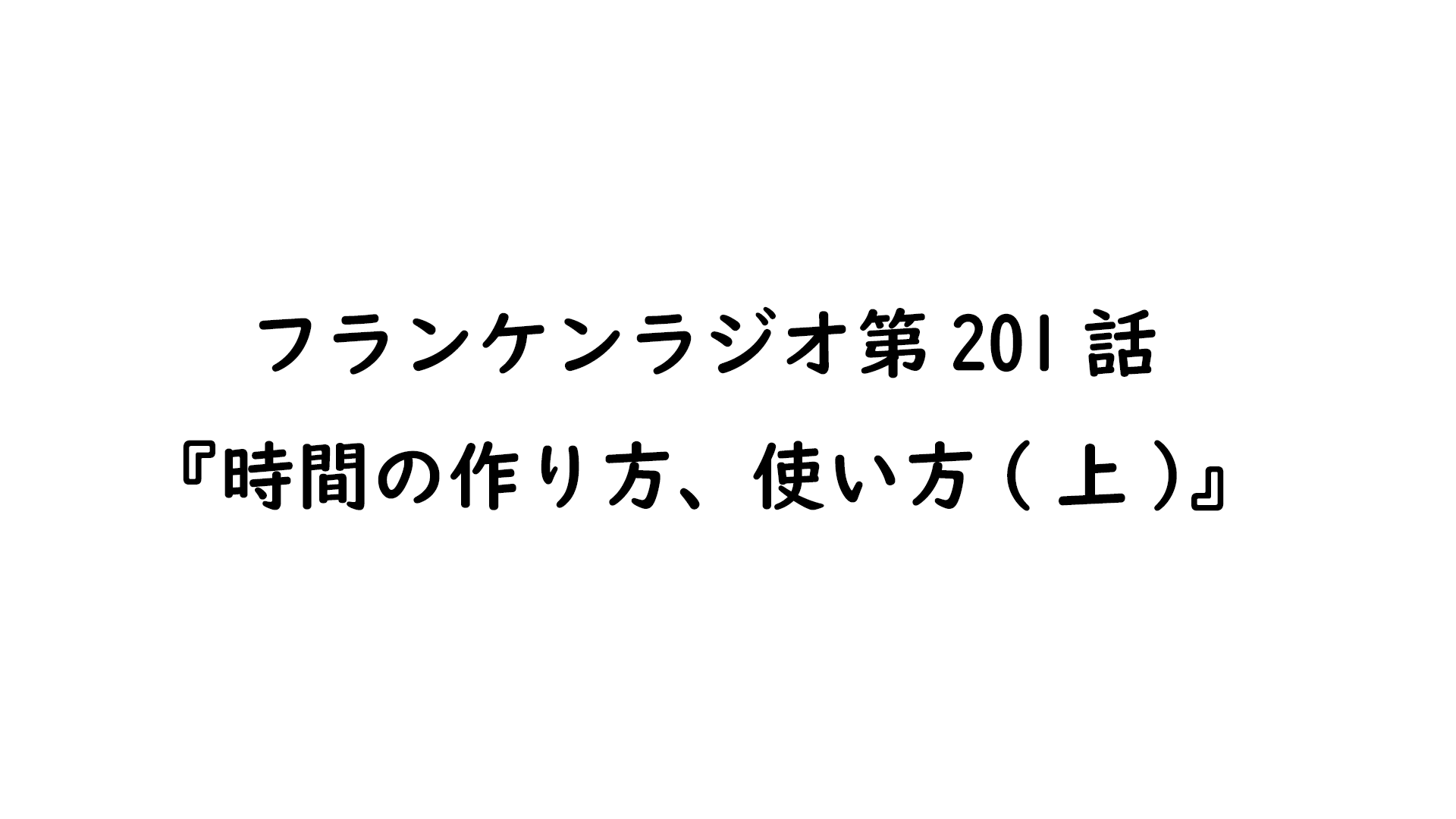第284話『本を読まない人』
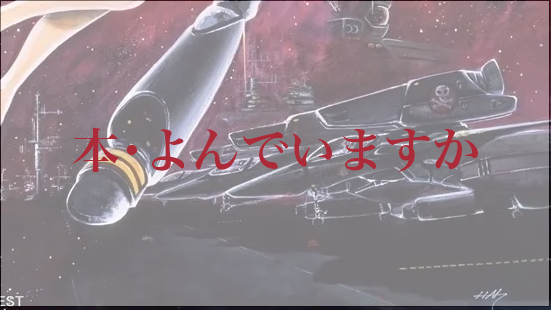
トラです。
本、読んでいますか?

フランケンラジオを聴き、こんな文字起しブログまでたどり着いてしまった読者の方(方々)はきっと日々忙しくされていることでしょう。
2024年には、なぜ社会人になると本を読めなくなるのかについて書かれた本が話題になりました。内容は「う〜ん」という出来らしいです。私は読んでいません。
私ですか?
本、あまり読めていません。積ん読が溜まりに溜まって、家の床全てを埋め尽くしてしまうのではないかという勢いです。勢いだけなので、広くない家の床半分を埋めればいいほうです。
そんな私のような勤め人の読書観に「喝!!」を入れてくれるのが、今回紹介するフランケンラジオ第284話『本を読まない人』です。
これまで読書関連回は幾度か取り上げてきましたが、なぜ読むべきか、難解な本をとりあえず舐めてわかった気にならないための方法に付いてお話されています。
では文字起しに続きます。
イントロダクション
はい、おはようございます。
フランケンの略道通勤ラジオです。
最近あれですわ。
ちょっと声張り上げる系のコンテンツをしばらくやっていたので、今日はちょっと落ち着いた感じでやっていこうと思います。
ヘッドセットを手に入れました
ヘッドセットを手に入れたんですよ。
年末に更新していた、すぐ消すシリーズってあったの覚えてますか?
あれね、すごくボソボソと喋ってる割には声がクリアだったコンテンツですけど、ヘッドセットを使って喋ってたんですよね。
ちなみにこれ、ヘッドセットが何でできているかというと、フェイスガードってあるじゃないですか。
なんかヘッドホンみたいなね、頭からあの、かぶって、口に、下の方からニョキッと腕が出て、それにフィルムが付いてるというフェイスガードをもらったので、こんなもんに使わねえよって言ってそのフィルムを外して、口の方にアームが出てるので、先にピンマイクをつけてみた。
そのピンマイクにあのね、パピプペポ音や破裂音を拾わないようなフェルトみたいなやつをつけてあげると、やたらと声を張り上げなくても、結構クリアな音声が取れるということに気がつきました。
そんなことやって遊んでるんですよ。
何の話だったっけ?
今日はピンマイクの話をするつもりじゃなかった、本の話だ。
具体的な本の話じゃないですよ。本を読む人と読まない人。
これね、本読む人の話ってやっぱり面白いなというね、そういう人に会ったんです。
多分、このラジオ聞いてくれている人の中で知ってる人はいるかな。でも、名前を出すのはやめておこう。
すごい博識で、本いっぱい読んでる人に会う機会があって、話を聞いたんです。
そうすると、やっぱりかなりの本を読んでることが伺えるんです。
これは、色んなことを知っているという以外に、その背景に本からのインプットがあって、さらにそれを咀嚼している。そういう感じに思える人と、そうでない人がいます。この「色んなことを知っている」というのは、いわばその人が使える武器が多いということです。
これは、多くの本を読んでいるという、インプットの数が担保している。
さらに、ただ読んでるというだけじゃない。その本が、自分の戦いでどういう武器として使えるのかという部分まで見て読んでいる。
これが噛み砕く、咀嚼という概念なんですよ。
それができてる人ってやっぱりすげえなという風に思った。そんな人に会ったという話。今日はそんな話をしましょう。
思考・話をパーツ(武器防具)の性能を担保する
まずですね、本を読んでいる人、そして本からのインプットを咀嚼できてる人って、思考のパーツというのが本から来てることが多いんですよ。
そのパーツ自体の強さとか価値は、本自体がもうすでに担保してくれてる。だから、武器として最初から成立している。その武器や防具を組み合わせて、戦術を展開する。
これが、いっぱい本を読んでいる人の戦い方なんですよね。
この戦い方、戦術というものが武器に担保されているというのは、とても大事な気づきなんですよ。
例えば、騎馬隊と戦う歩兵だったら、刀で戦わないで柵を作り、パイク、長やりで迎え打つ。そして馬の勢いを止めたら弓で制圧する、みたいな。
そういった戦術というのは、柵が一瞬で蹴散らされたり、パイクが折れたり、弓が飛ばないとか、そういう武器でないという性能が担保されてないと話にならないじゃないですか。
戦えないんですよ。
だから話をする時、特に何らかの繋がりや流れや到達点があるような話をする時には、そこに到達するための戦術を成り立たせる武器の性能、すなわち話のパーツというのがしっかりしている必要がある。
そのパーツのかなりの部分というのは、書籍から来ていると思うんですよ。
著者と同じエネルギーをかけずにメッセージに至る
1冊1冊の本って、著者が人生のかなりのエネルギーをかけて作ったものです。
ですから、自分が本を読まないで同じようなメッセージに至るためには、同じようなエネルギーが本来必要になるはずなんです。結論に効率良く到達するためには、自分でうーんって考えるよりも、その本を読んだ方が早いんですよ。
話がうまいというか、ストーリーを構成して、ある目的のためのゴールに落とし込む。この作業がうまい人は、その武器の数が多かったり、武器の組み合わせが奇抜だったりするんですよ。
腕力があって武器を持ち、その武器を効果的に使う訓練もしている。
だからそういう人が発信する情報は強い。
世の中には情報を発信できている人がいて、発信したいという人もいます。
でも、それぞれに何らかの情報はどちらの人も外に出しています。この『武具を仕入れる』という概念が弱い人は本を読まない人だよね。
そういう人は今言ったような、武器の使い方がちゃんと分かっている人の武器が見えないんですよ。
自分が武器を仕入れて使うという概念を持ってないから、相手が使っている武器が目に入っていない。
だから、素手で戦ってるように見えているんですよね。
だから、武器を組み合わせた戦い方を見るとね、すごい強い じゃなくて すげえ腕力だなあ と評価する傾向にあると思います。
強さは理解できる。でも、武器の存在が見えない。だから、強さの理由が分からない。
情報発信が下手な人ってそうなんです。そういう人は武器を作る能力がないので、素手で殴る。
または、その場で目についた武器を拾って戦おうとする。
落ちてた石とか拾って適当に投げてみるとか、そういうことをやるんですよ、付け焼き刃で。
相手も素手だったら、それでも勝てることあるけれども、たまたま落ちていた石を、自分の武器になるところまで持っていけない。
だから、砂漠とか石も落ちてないような場所に行ったら、武器がないから戦えない。
素手で殴るしかなくなる。
そんな感じなんですよね。
だから、先人たちが武器として鍛えた道具、書籍をありがたく頂戴するという準備は常にしておく方がいいという風に、僕は常々思ってるんです。
この準備をやっていないと、自分が殴られた時に何で殴られてるのかが分からなくて、素手で戦おうとして負けるってことをやるんです。
武器の体をしていない道具を磨くには
今日の話、ここからが本題です。
先人の道具。道具ってさっきから言ってるけれど、本のことです。本って、結構道具の形をしていないことが多いんですよ。
これがミソですよ。
道具としての構成というのは、その本のメッセージの中にもう出ている。だけども、割と磨かれてないことが多くて、最後に一磨きしないと武器としては機能しない。
そんな形になってるんですよ、多くの書籍って。そして、間違った磨き方をすると、柄と槍先を逆に構えちゃうみたいな目に合うんです。
そんなものが多いんですよね。
こういうものを、自分で磨いて強い武器にしていく作業って、実は相当に難易度が高いと思います。
だから僕はこのね、武器の磨き方というものを勉強しないと、いくら本を読んでも武器としてストックするということはできないんじゃないかなと思うんですよね。
解説書のススメ
そういう意味で、本の解説書というのは一定の役割を持ってるとは思うんです。
『この武器は変な磨き方をすると、ちゃんと機能しない』という風に、この本をどう読むべきかという、お手本を解説してくれる。
本の解説書というのは、ある程度そういうスキルを持ってない人に役に立つと思うんですよ。
だから、本の解説書の類いはダメだという人がいるけれど、入りとしてはアリだと思ってるんですよ。
”解説書から入る”というのは。
例えば、サウザーさん(聖丁)と話していると、学生時代に本を読みすぎて思考の型をしっかり持っていることが分かる。
並の文化人では立ち打ちできない型というのが既に魂の深いところにカチッとできていて、解説本なんかを読むと、その解説本が原著をちょっと変な形で説いてしまってるように感じちゃう。
あそこまで読み込んでいると、ミケランジェロみたいです。ミケランジェロの言葉にこういうのがあるんですよ。「彫刻家は石から彫刻を掘り出すのが仕事だ」*ってね、ミケランジェロは言ったんですよ。
*『 わたしは大理石を彫刻する時、着想を持たない。「石」自体がすでに掘るべき形の限界を定めているからだ。わたしの手はその形を石の中から取り出してやるだけなのだ』
本を読んでいる人の目には、原著から掘り出すべきメッセージの形というのがはっきり見えてる。それなのに、解説書がお粗末な掘り方をすると見ていられないんですよね。
だから、ものすごく思考の型がはっきりしていて、この本からはこういったメッセージを取り出すべきだというのが頭から見えちゃってる人が他人が書いた解説書を見ると「だめだ。これは読まない方がマシだ」となる。
だから原著に当たれという風に言うんですよ。ただ、掘り方も何にも知らないという人には、それは結構きつい。ある程度解説というのはあってもいいと思う。
僕は、優れた彫刻家が石の中にどんな彫刻を見い出すのかという、そのプロセスを学ぶことが、1番大事だと思っている。
そのために、解説書の活用は役に立つと思います。
まず1つ大事なのは、彫刻家というのがその世に出してくる彫刻、解説書がある。
それは既に彫刻家が掘り出してしまった1つの形なので、それ自体を眺めても彫り方の勉強にはならないん。これを分かっておかないと、いけません。
この解説書から学ぶポイントは何かというと、その彫刻の良し悪しを見るんじゃなくて、原石からその人がどうやって切り出したかという、手順を学ぶことなんですよ。
だから掘る過程を見なきゃいけないんですよね。
完成品の彫刻には、その過程が乗っからない。
じゃあどうすればいいのかというと、解説書を読む時には原著も一緒に読むべきなんです。
ここで言う掘る前の原石というのは原著のことです。
彫刻というのは解説本のことですよ。
原石から掘る過程で、彫刻家がどういう彫刻をその中に見い出したかというのは、これを見比べて初めて分かるんですよ。
それが、掘り方を学ぶということなんですよ。
こんなことを書くと、じゃあ2冊読めってことかとゲンナリしちゃう人もいるかと思うので、テクニック的なこともちょっと触れておきましょうか。
あんまり本質的じゃないからあれなんですけども。
やり方が分からないと、始められないでしょうから。
『読まなくていい本の読書案内』から見る武器の作り方と使い方
解説本と一緒に原著に触れるやり方。
まず、解説本から先に手に取って読み始めていい。
でも、解説本はストレートなものじゃない方がいい。
例えば、『カント入門』みたいな本から入ると、そのカントの分身に殴り殺されることになっちゃうから。
解説本を書いてる人が何らかのグランドミッションみたいなものを持っていて、そのミッションを成り立たせるためにパーツとして原著の一部に言及する。そういう解説部分を読むのがいいです。
紹介されたグランドミッションの中で、どういうパーツを切り出したいのかという意思が明確になってる部分があり、紹介された部分に関して原著をあたってみる。
原著の当該部分と照らし合わせて、切取り方と切取った彫刻を、解説本の著者がどうやって自分の武器として本の中で活用していくのか。
ここの作業を、読み比べて学ぶといいんです。
分かります?
縮小コピーみたいな解説を読んじゃダメだってことなんですよ。
自分のテーマにぴったりあったような武器として文献を引っ張ってくる時に、どうやって切り取ったかをここで学べという話をしてるんです。
具体的に何か例を挙げるとすると、橘玲の『読まなくていい本の読書案内』という本があります。
この中に行動経済学について言及するセクションというのがあって、エリック・バーカーのあの『残酷すぎる成功法則』とか、ダン・アリエリーの『予想通りに不合理』という本が出てくるんですよ。
その切取り方は、原著を読んでいるとちょっと原著の持っているメッセージとニュアンスが多少違うと感じる。
けれど、この原著という原石から、橘玲がまとめたい本を作るためにどんな彫刻を見い出して切り取ったかという、この部分が分かるんですよ。
武器の作り方というのも分かるし、武器の使い方というのも同時に分かる。
そういうもんなんですよね。
まとめ
ちょっと長くなってきたんで、そろそろまとめに入りますか。
今日の話は、何かメッセージを出していきたい人は、武器が足りないとそもそも戦闘するための戦術というか、戦い方を組み上げることができないというところから入りました。
だからまず、戦い方どうこうを言う前に、武器を作るプロセスというのを持たなきゃいけない。
それを学びなさい、というのが今日の大切なメッセージになります。
トンカチを持つと振りたくなる
まあ、その話をすると「どんな武器を作っていけばいいんですか?」
「そもそもあなたはその武器で何と戦いたいんですか?」
という部分が次なる疑問点として出てきますが、今日は手をつけませんでしたよ。
この話については、またどっかで考えていきましょう。
あー、そうだ。
この話をしようかなと思ったのが、武器を手にすると人間は使ってみたくなるってやつです。トンカチを持つとみんな釘に見えてきて、トンカチを振りたくなるっていうんですよ。
そうやって使ってみて、初めて武器の使いどころというのが見えてくる。
そういう話をまたしていきましょうかね。