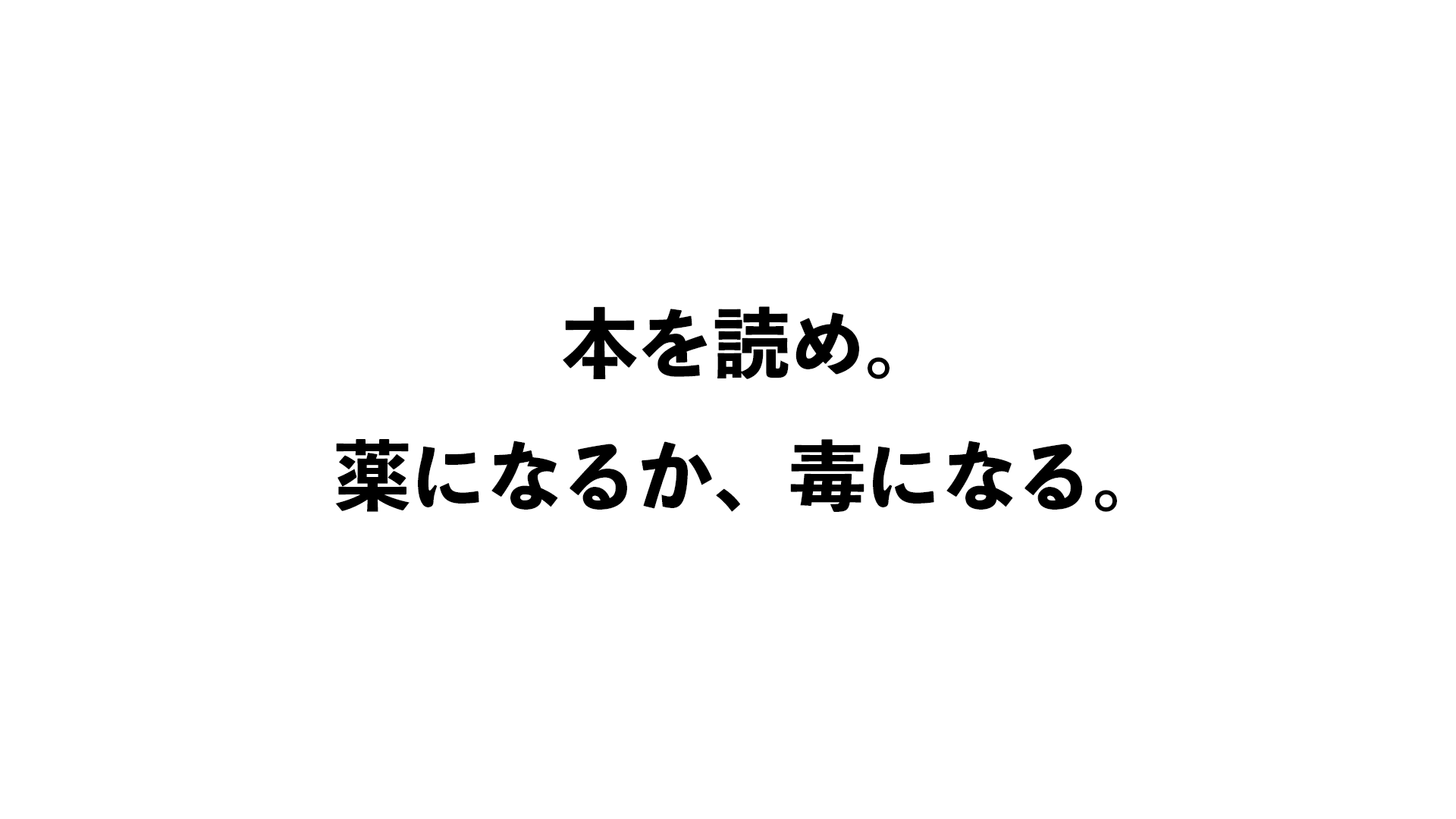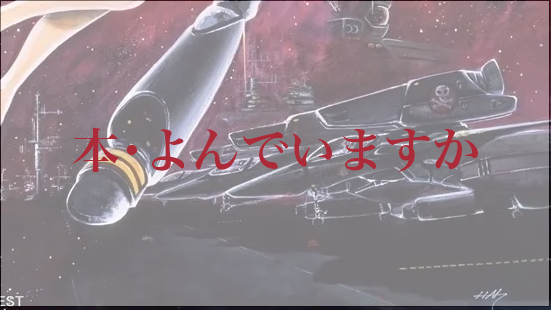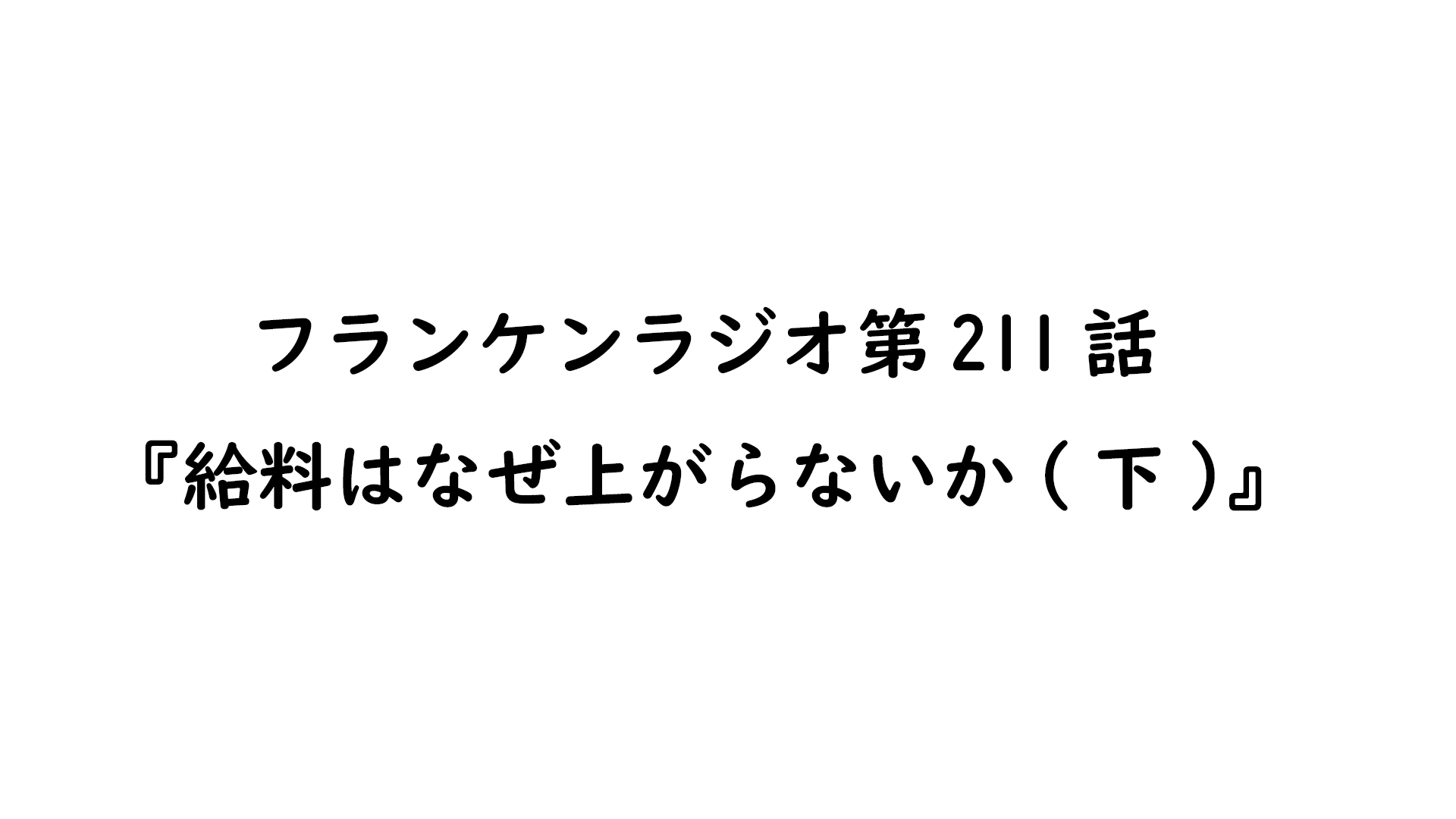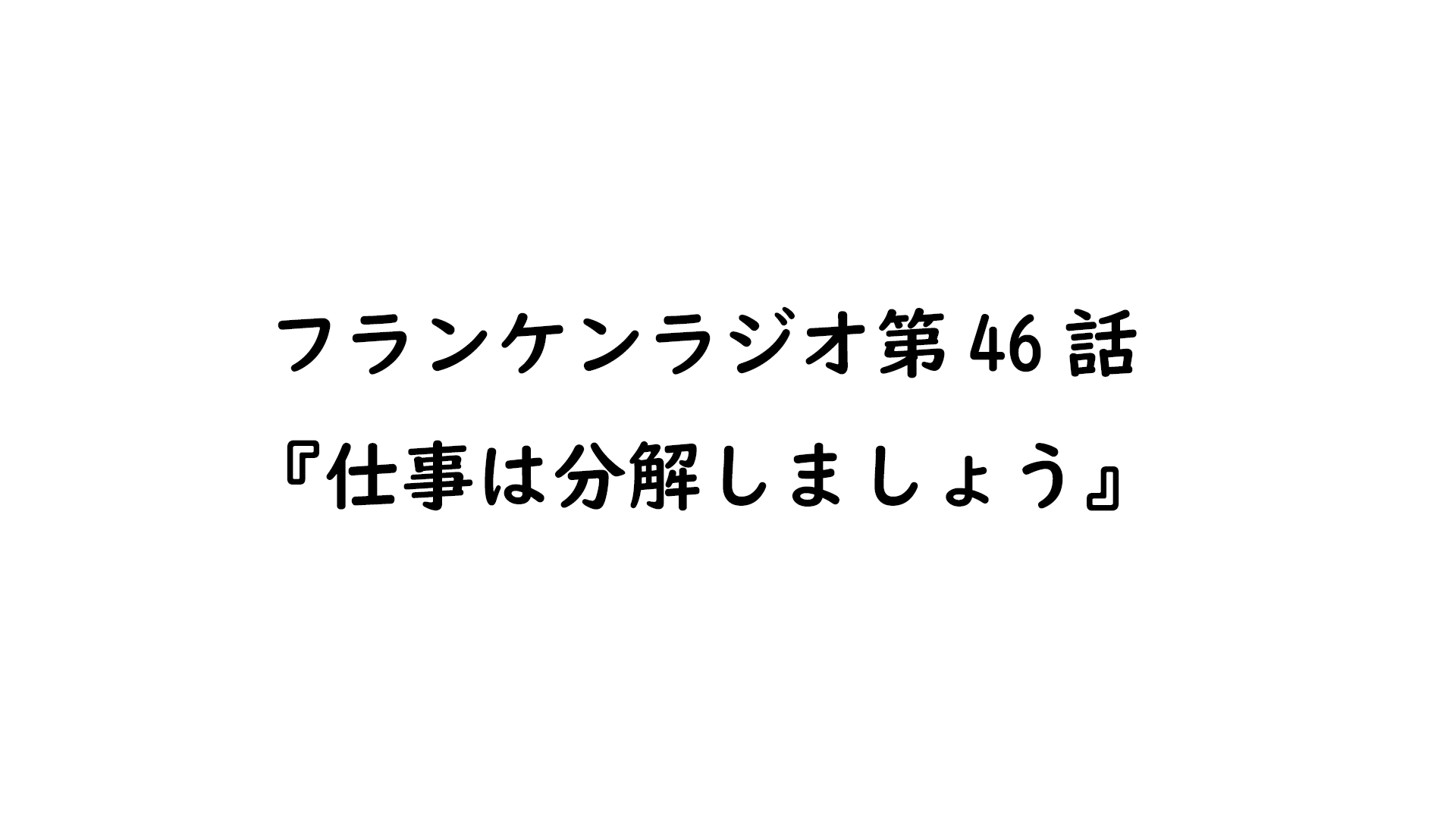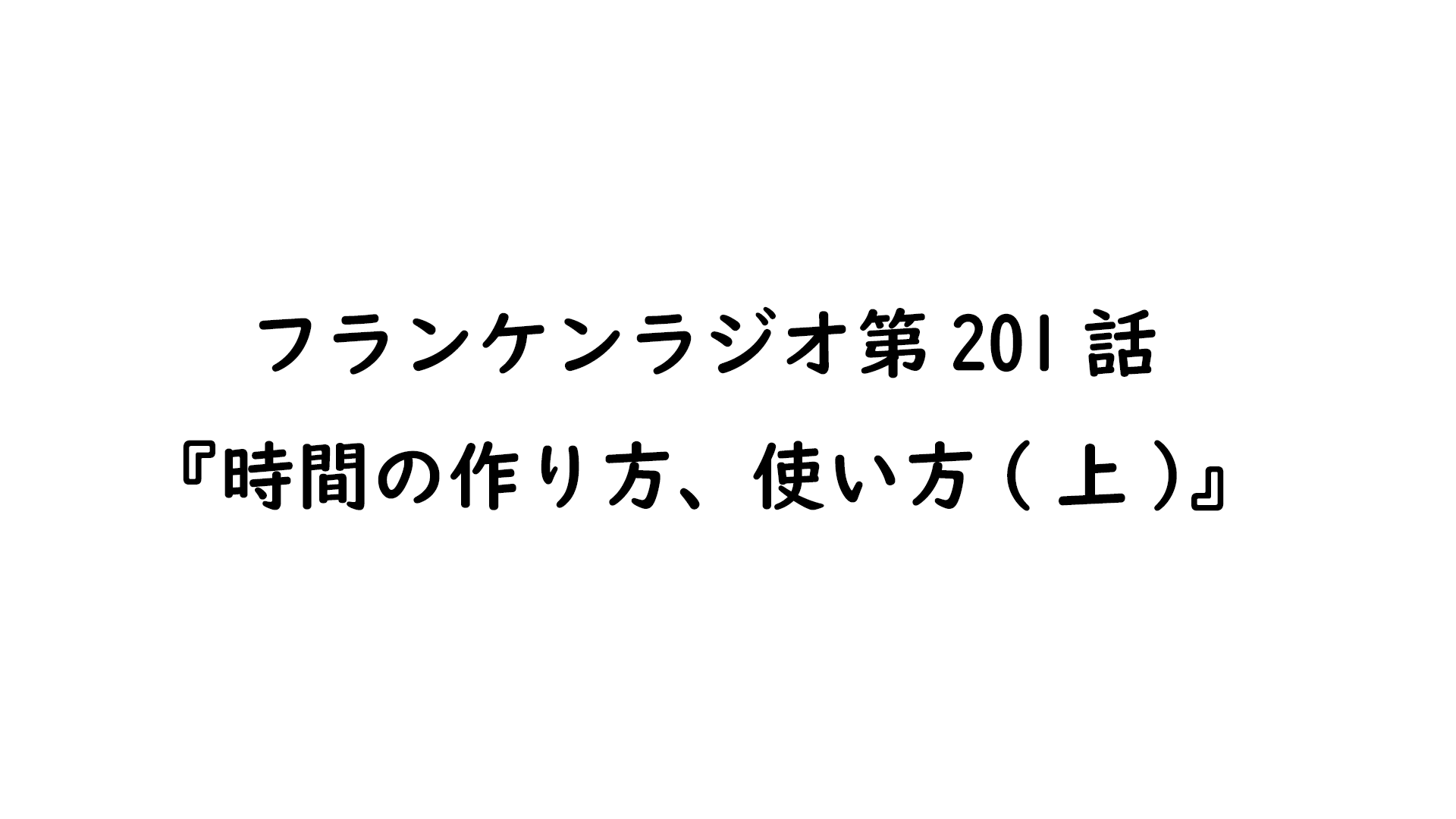第283話『停滞』タイムスパンと評価の話
トラです。
1つの勤務先で同じ仕事を長く続けていると、
「この先ずっとこんな仕事の毎日が続くのかな」と思うことってありませんか?
そんなわけがないのだけれど、大企業ですぐに潰れる心配がない正社員だと油断してルーチンワークに甘んじているという人が多いように感じます。
「継続は力なり」「継続こそが力なり」とは言うけれど、果たして本当にそうなのか?
「無駄な努力」という言葉もあるが、これも真理なのか?
今回は、そんな疑問に答えてくれるようなラジオ回の文字起こしになっています。
イントロダクション
はい、おはようございます。フランケンの略働通勤ラジオです。
今日はですね、 同じ仕事を頑張るタイムスパンの話をしましょうか。
2年間、2年間です。
自分がすげえ頑張って真面目にやってきたという感想を持っているにも関わらず、自分が今やってることは2年前とほぼ同じ。
だったら、少なくともその事業に関して成長の可能性はもう期待できない。僕はそう思います。多分そういうもんですよ。
『石の上にも3年』って言うじゃないですか。
これね、2年で止めた方がいい。
今日はそんな話をします。
自己評価とキャリア資産の重要性
ちょっと前までは、5年って言ってたんですよ。
でも、今は2年だと思う。
本気で2年頑張って、その世界でのプレゼンス・存在感が上がっていかないようだったら、
おそらく自分にその業界の適正がないんですよ。
長い間、その理由が分からなかった。
でも最近、ぼんやりと分かってきたような気がします。
成長を左右するフィードバック
おそらく、フィードバックのスピードなんですよ。
初めて自分が曝露された環境で手探りで関わり、決算期を一度迎えるとします。
その時に、自分の行動の何が評価され、何が評価されなかったのかを解析する。
このフィードバックをやらない人というのが、世の中に結構いるんですよ。
最初に何かを始める時に、このアクションはおそらくプラスに作用するだろう、評価を受けるだろう、と仮説を立ててアクションしてみる。
大抵の人がそうだと思います。
でも、その世界のことが全然分かってない時はその仮説というのが結構間違っていて、思ったよりも業界内の評価に繋がらなかったりすることがある。
仮説が当たらなかったり、売れなかったりね。
あるいは、評価されたとしてもその評価ポイントが始める前に想定していたものと全然違うものだったりするんですよ。
そういうことを感じながら軌道修正し、最終的に一度決算期を迎えると、大体仕事に対する総括というものが一回なされるわけです。
ここで、普通は色々と考えると思う。
思ったよりも評価に繋がらないアクションだったなとか、評価されているけど割に合わなかったなとかね。
そんなこんなで新しい会計年度がスタートしたら、昨年度までのフィードバックを活かして効果的な身の振り方、手綱の取り方をしていく。
これね、上から振ってくる仕事とかノルマとか、そういう話に還元してもいいです。
やらされ仕事でもいいですよ。
昨年と全く同じ案件が降って湧いたとしても、少なくとも1年の会計年度を跨いだら、自分は違う身の振り方をするようになるだろう。という意味です。
同じ仕事が降ってきても、もう1年回して、2度目の決算期をまたぐ時に補正した2年目の評価というのが出るわけです。
他者評価ではなく、自己評価で適性を判断する
『評価』というと、なんか誤解する人が出るか。
これ、勤務査程とかボーナスとか、そういう即物的なものを言っているんじゃないですよ。
もっと言語化しにくい、組織の中におけるキャリア資産みたいなものを貯められたかどうか。
こんな主観的な評価です。
僕はね、生涯にわたって他人からの定量的評価というものに関心がなかった。
評価という単語を使う時は、いつも自分で自分を評価する一人称的視点を意味しています。
この枠組の中に、自分のキャリア資産というのを積めたのか積めなかったのかという、自己評価を2度目の決算をまたぐ時にするんですよ。
決算期を2度またいでも、全く評価がこの世界で貯まっていかない。
主観的にも成長が感じられない。
やってること、やらされてることが客観的にも2年間全く変わらない。
そうであれば、僕にはこの領域の適正はないなって思うんですよ。
だから、この領域からはもうすっぱりと手を引きます。
なぜなら、この領域では伸びないという自覚が既にあるからです。
この”すっぱり手を引くこと”ができなくて、ズルズルやっちゃう人って結構いるんですよ。
これはね、本当に時間の無駄。さっさと別の領域を見つけた方がいい。
給料ベースアップはコスト節約のお小遣いでしかない
気をつけて欲しいのは、自分には全く何も貯まってないにも関わらず、他人に都合よく使われているケースがあるんです。
そんな時は見た目だけ、何かが増えてることが多い。
何が増えてると思います?
給料です。
給料が増えて、これ以外に何も自分に積み上がってないというパターンが結構ある。
これ、なんとなく自分が評価されてるように感じちゃうかもしれないけれど、給料が増えることって意味ないですからね。騙されちゃいけませんよ。
『定額ベースアップ』なんて評価じゃなくて、リクルーティングコストと教育コストの節約分というのがお小遣いとして乗っかってるだけなんですよ。実務が変わらないで給料が上がるって、そういうことだから。
誰かに辞められて新しい人を見つけてくるには、結構なリクルーティングコストがかかる。
コストをかけて採用した人を使えるようにするのにも、結構な教育コストがかかる。
毎年辞められて、それを誰かに新しく教育する代わりに、あなたがその場所で永久に踏み台昇降運動みたいなのを続けてくれるんだったら、喜んでお小遣いをあげちゃう。
『ベースアップ』って、本来そういう意味ですからね。
仕入れる時に一山いくらでガサっと雇ってきて、集団で反復横飛びとか踏み台症候運動をさせていると、たまに集団の中に間違って紛れちゃった規格部外品みたいなやつがいる。
これはね、ピックアップして規格品とは違った使い方としてストックするわけですよ。
なんかちょっと面白いのが混ざってたって。シラスの袋の中に、たまにちっちゃいタコとかちっちゃいイカ入ってんじゃん。ただそれって見つけたらさ、ちょっと避けておいて、すぐは食べないでしょう。
そういうもんですよ、企業って。そういう成り立ちをしているんです。
『ルーチンワーク』という名の踏み台昇降運動
踏み台昇降運動とか反復横飛びって、別の言葉にすると『ルーチンワーク』って言うんですよ。
このルーチンワークをやってもらえるだけでも、企業には利益が出るようになっている。
そこまで手順は分解されています。
だから、油断するとやらされる方は永久にルーチンワークをやらされることがあるんです。
新しいのを見つけてくるのが面倒という理由で、30年とか平気で。同じ反復横飛びする機械にセットして、放置したりしますからね。
そして新しい人が見つかったら、平気で肩をバットでガーンってぶったたいてくるんですよ。
それをひどいって言っちゃうのは、ちょっと脇が甘いっすわ。
そういった、バットで肩をぶっ叩かれるリスクを避ける意味でも、無意味なキャリア浪費をしないという意味でも、2年間で何も得るものがない環境というものからは手を引くということを僕は強くお勧めします。
昇給しても、金を積まれたってしょうがない。
本当に活かせるキャリアというのは、多分単純に金でトレードされないものなんです。
自分で自分のキャリアとかスキルを金に変えるというのはいいんです。でも何にも変わらないで、金だけ積まれるって意味がないです。
相手があなたのキャリアに値段をつけてくるような場合というのは、大抵買い叩かれてます。
2年、2年ですよ。
2年やって自分の評価が主観的に自分の中で変わらない、上がっていないと思ったとき。
そして、客観的な評価も実は変わってないだろうなという時はその事業から手を引いたほうがいいです。
客観的評価を得るのは外部から
ちなみに客観的な評価というのは、変わるときは内部からより外部から変わっていきます。
一般的な組織では、ルーチンワークをしてる人間をニュートラルな意味で評価するシステムというのはほとんどない。
ルーチンワークをやっている自分というのがもしいたとしたら、そのちょっと上の階層に鎮座している奴というのは部下がちゃんとルーチンワークを真面目にやってるかどうかを見てるだけなんですよ。
そもそも、歯車以外の使い方をしようにも、歯車以外に使えるというのをそのレベルの人間が発掘しても、ちょっと上の階層に鎮座してるやつらには、上に上げるチャンネルがない。
そういう人たちが何をやっているかというと、歯車の動きが悪くなった時だけアラーム鳴らせって言われてそこに座ってて見てる。その程度なんですよ。
だから客観的評価って大体は外部からの評価で上がってくんですよ。
内部からの評価じゃないんですよ。
外部評価というのが溜まっていくと、2つぐらい上の階層の、「オタクのところにいる誰々君、あれいいね。世話になってるよいつも」なんて評価というのが、外から2つ3つ上の階層に入ってきて「誰だっけ?それ」と思い調べてみると「確かに。こいつ調べてみるとなんか物が違う」みたいな感じで発掘されるんですよ。
隣の階層の人間にポテンシャルは評価できない
組織という生き物は、隣り合った階層間で個体値というのがそんなに離れていないところが面白いんですよ。
そういうかけ離れてないタスクを与えられてるから、お互いのポテンシャルを評価する能力というのがないんです。似たり寄ったりだから。
でも、2階層ぐらい離れると違う顔付きのユニットは違うように見える。
初めて見えてくるんですよ。2階層も離れると。そういうもんなんですよ。
周りにもいるでしょう?
ダンゴになっている集団で、この集団の兄弟子みたいなやつをちょっと持ち上げるのがね、あの最適解みたいなゴマすり集団。
その中から、さらにその上の層に引っ張り上げられるのって、兄弟子が選んだお気に入りの子分じゃなくて「なんでこいつが選ばれるんだ?」的な変なやつだったりすることあるでしょう。
ああいう感じなんですよ、常に。
複数領域に同時にエフォートを突っ込む2年間にしろ
2年やって自分のエフォートを突っ込む領域、この領域のプレゼンスが上がっていかないという時は、やっぱりそれ以上突っ込んでも多分芽は出ない。
あの、最後に、ま、こういう言い方すると2年突っ込んでみてダメなら別の方向にまた2年という風なね、そういう捉え方する人多いんですよ。
これだとね、あっという間にね、人生そのものが終わっちゃうんです。
若い頃に自分を何かの形で上に上げてくチャンスって。スタートから10年ぐらいしかないんです。正直そのぐらいで、なんとなく選択肢というのが決まっちゃう。
だから複数の方角に同時にねエフォートというのを突っ込まないとダメなんですよ。
最低3つぐらい。
1つ1つは最長2年突っ込む。
だから3つ、4つぐらいを同時にやって、芽が出ねえなというのはザバザバと2年以内に切っていくというのを、並行してガンガンやってくんですよ。
それで10年以内に自分の人生にカタをつけるというのを若いうちからやらないと無理ですよ。
2年やってダメなら次というやり方やっちゃ絶対ダメですよ。
やってみて全くダメだなって思ったら、もう2年も粘ばらずに半年くらいである程度見切りをつけて新しいテーマというのを模索していく。
この作業も、同時にやらないとダメです。
そういう感じで、5年で10個ぐらいかな。
5年間のうちに10個ぐらいの方向性を持つイメージでやるのがいいですよ。
そん中で1番カツっとね、自分の中で大当たりしたものというのに乗っていく。
そうすりゃ大体ね、どれかしっくりするものに出会います。
世の中、そういう仕組みになっているので、 1つの案件へのフルコミットは成長が認められないと思ったら2年でやめる。
この2年は縦に繋がずに3つ4つ必ず並列でやってください
目標としてはね、5年で10個ぐらいの方向性というのは考えながらやるというのが鉄則だよという、そういうね、ちょっときついけれどもね、それやんないと多分戦っていけない。
世の中そうなってますという話でした。